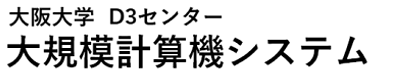2021.05.10
目的・プログラム
Day1
本センターの新スーパーコンピュータSQUIDに導入されている最新のGPU NVIDIA A100の概要と特徴を把握するとともに、A100を利用するためのOpenACCプログラミングの基礎を学びます。
| 5月26日(水) |
| 10:30 - 10:45 |
SQUIDの概要(計算ノード) |
| 10:45 - 12:00 |
最新GPU NVIDIA A100の概要と特徴 |
| 12:00 - 13:00 |
昼食休憩 |
| 13:00 - 15:30 |
OpenACCとNVIDIA HPC SDK |
※当日の進捗状況に応じて前後する可能性がございます。
Day2:
本センターの新スーパーコンピュータSQUIDに導入されている、相互結合網であるNVIDIA Mellanox InfiniBand HDRの基本を把握し、その技術を生かすRDMAプログラミングの基礎を学びます。
| 5月27日(木) |
| 10:30 - 10:45 |
SQUIDの概要(インターコネクト) |
| 10:45 - 12:00 |
NVIDIA Mellanox InfiniBand HDR基本技術 |
| 12:00 - 13:00 |
昼食休憩 |
| 13:00 - 14:30 |
RDMAプログラミングの基礎 |
※当日の進捗状況に応じて前後する可能性がございます。
受講に当たってのご注意
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本セミナーはオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。接続方法については、別途連絡いたします。
2021.04.27
本説明会は4月26日に開催した「スーパーコンピュータSQUID利用説明会(スーパーコンピュータ経験者向け)」と同じ内容です。
概要
本説明会では、5月から運用開始したスーパーコンピュータSQUIDを中心に、その特徴や利用方法、申請方法について説明します。大阪大学、あるいはそれ以外の計算機センターですでにスーパーコンピュータを使ったことのある方を対象とします。
受講に当たってのご注意
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本説明会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
プログラム
| 13:00-13:20 |
趣旨説明(サイバーメディアセンター 応用情報システム研究部門 伊達 准教授 ) |
| 13:20-14:50 |
SQUIDの利用方法(日本電気株式会社) |
| 14:50-15:30 |
利用申請方法(情報推進部 情報基盤課 技術職員) |
説明会資料
2021.01.22
本シンポジウムは終了いたしました。大変多くの方にご出席いただき、大盛況のシンポジウムとなりましたことを心よりお礼申し上げます。
(参加者数:122名)
概要
開催日:2021年3月16日(火) 10:30 - 16:30 (接続受付 10:00 - )
形 式:オンライン配信
参加費:無料
主 催:大阪大学 サイバーメディアセンター
共 催:スーパーコンピューティング技術産業応用協議会 (ICSCP)
協 賛:学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点 (JHPCN)
ねらい
今回のシンポジウムでは、2020年にスーパーコンピュータシステムを導入した大学計算機センター、および、スーパーコンピュータの産業利用・応用に取り組む機関から専門家をお迎えし、スーパーコンピュータシステムの目的、役割、利活用事例を踏まえながら、スーパーコンピューティングを活用した産学共創の今後の課題と将来を考えていきます。
プログラム
| 10:30-10:40 |
開会の挨拶 |
|
下條 真司 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
センター長・教授 |
| 10:40-11:30 |
基調講演1
「東北大AOBAの運用開始と将来展望」 |
|
滝沢 寛之 |
東北大学 サイバーサイエンスセンター
副センター長・教授 |
| 11:30-12:00 |
「新スーパーコンピュータSQUID稼働に向けて -産学連携・産学共創への期待-」 |
|
伊達 進 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
応用情報システム研究部門 准教授 |
| 12:00-13:00 |
昼食休憩 |
| 13:00-13:50 |
基調講演2
「スーパーコンピュータ『不老』導入と産業利用の新展開」 |
|
片桐 孝洋 |
名古屋大学 情報基盤センター
大規模計算支援環境研究部門 教授
|
| 13:50-14:30 |
「ものづくりにおけるスーパーコンピュータの利活用事例」 |
|
松岡 右典 |
スーパーコンピューティング技術産業応用協議会 企画委員長 /
川崎重工業株式会社 航空宇宙システムカンパニー
|
| 14:30-14:40 |
休憩 |
| 14:40-16:20 |
パネルディスカッション
「スーパーコンピュータの産業利用と今後の産学共創のあり方」 |
|
座長 |
山下 晃弘 |
大阪大学サイバーメディアセンター
応用情報システム研究部門 招へい教授 |
| パネリスト |
江川 隆輔 |
東北大学 サイバーサイエンスセンター
スーパーコンピューティング研究部 客員教授 /
東京電機大学 工学部 情報通信工学科 教授
|
| 大島 聡史 |
名古屋大学 情報基盤センター
大規模計算支援環境研究部門 准教授 |
| 木戸 善之 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
応用情報システム研究部門 講師 |
| 高原 浩志 |
計算科学振興財団 (FOCUS)
シニアコーディネータ / 研究部門長 / 人材開発グループ長 |
| 松岡 右典 |
スーパーコンピューティング技術産業応用協議会
企画委員長 /
川崎重工業株式会社 航空宇宙システムカンパニー |
| 16:20-16:30 |
閉会の挨拶 |
|
降旗 大介 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
副センター長・教授 |
申込に当たってのご注意
講演資料
参考資料
2020.12.22
概要
開催日:2021年3月10日(水)13:30-17:20、2021年3月11日(木)13:30-16:50
会 場:オンライン配信
参加費:無料
プログラム
2020年度 公募型利用制度 成果報告会 1日目
日時:2021年3月10日(水)13:30 - 17:20
司会:安福 健祐 (大阪大学サイバーメディアセンター 准教授)
|
13:30-13:35 |
開会の挨拶 |
|
|
菊池 誠 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
教授 |
| 【若手・女性研究者支援萌芽枠 セッション I】 |
|
13:35-14:05 |
「ハイブリッド汎関数を用いた固液界面の第一原理分子動力学シミュレーション」 |
|
|
大戸 達彦 |
大阪大学 基礎工学研究科
助教 |
|
14:05-14:35 |
「格子QCDを用いたhidden-charm pentaquarkの解析」 |
|
|
杉浦 拓也 |
理化学研究所 数理創造プログラム
特別研究員 |
|
14:35-15:05 |
「自己組織化イオン結晶におけるナノ相分離様態と分子輸送特性のインタープレイ」 |
|
|
石井 良樹 |
兵庫県立大学 シミュレーション学研究科
特任講師 |
|
15:05-15:20 |
休憩 |
| 【大規模HPC支援枠】 |
|
15:20-15:50 |
「Z3対称な量子色力学における格子シミュレーション」 |
|
|
河野 宏明 |
佐賀大学 教育研究院
教授 |
|
15:50-16:20 |
「QCDの非可換ビアンキ恒等式の破れ(モノポール)に基づく新しい閉じ込め機構の
モンテ・カルロ法による研究」 |
|
|
鈴木 恒雄 |
大阪大学 核物理研究センター
協同研究員
|
|
16:20-16:50 |
「発光ガラス材料における光吸収・発光時の電子・格子ダイナミクスの計算科学的
探索」 |
|
|
宮本 良之 |
産業技術総合研究所 機能材料コンピュテーショナルデザイン研究センター
上級主任研究員 |
|
16:50-17:20 |
「Gradient flowに基づくSFtX法による物理点QCDの熱力学特性の研究」 |
|
|
金谷 和至 |
筑波大学 宇宙史研究センター
教授 |
※発表は25分、質疑は5分の予定です。
2020年度 公募型利用制度 成果報告会 2日目
日時:2021年3月11日(木)13:30 - 16:50
司会:宮武 勇登 (大阪大学サイバーメディアセンター 准教授)
| 【若手・女性研究者支援萌芽枠 セッション II】 |
|
13:30-14:00 |
「環状鎖メルトへの線状鎖の少量添加の粗視化MDシミュレーション」 |
|
|
上原 恵理香 |
お茶の水女子大学 ソフトマター教育研究センター
特任助教 |
|
14:00-14:30 |
「タンパク質-リガンド結合自由エネルギーにおける共溶媒濃度依存性の解明」 |
|
|
肥喜里 志門 |
大阪大学 基礎工学研究科
特任研究員 |
|
14:30-15:00 |
「分子設計に向けた微孔性高分子膜によるガス分離能の分子動力学シミュレーションによる解析方法の開発」 |
|
|
小嶋 秀和 |
大阪大学 基礎工学研究科
特任研究員 |
|
15:00-15:15 |
休憩 |
| 【若手・女性研究者支援萌芽枠 セッションIII ・ 人工知能研究特設支援枠】 |
|
15:15-15:45 |
「ミウラ折り型ジグザグリブレットの実用のための研究」 |
|
|
岡林 希依 |
大阪大学 工学研究科
助教 |
|
15:45-16:15 |
「自動矯正歯科診断AIシステムの開発」 |
|
|
谷川 千尋 |
大阪大学 歯学部附属病院
講師 |
|
16:15-16:45 |
「IoTビッグデータからのイベント予測による異常検知ソフトウェアの開発」 |
|
|
本田 崇人 |
大阪大学 産業科学研究所
特任助教 |
|
16:45-16:50 |
閉会の挨拶 |
|
|
木戸 善之 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
講師 |
※発表は25分、質疑は5分の予定です。
2020.12.15
サイバーメディアセンターで運用中のスーパーコンピュータ SX-ACE は2021年2月末で運用を終了し、2021年5月より次期スーパーコンピュータ SQUID を稼働開始予定です。SQUIDの導入を記念して、当センターのSX-ACEをお使いのユーザを対象にSQUID ベクトルノード群(SX-Aurora TSUBASA)での高速化が見込まれるプログラム(非商用)を募集いたします。応募者多数の場合は、SX-ACEからSX-Aurora TSUBASAへの移植の困難さ、本センターの利用履歴等からサイバーメディアセンターにて対象者を選定し、お申し込みいただいてもお断りする場合がございますので予めご了承のほどよろしくお願 い致します。
ご興味・ご関心のあります方は是非ご応募ください。
募集要項
| 募集期間 |
12月24日(木)- 1月15日(金) |
| 応募資格 |
本センターのSX-ACEのユーザ |
| 対象プログラム数 |
若干数 |
| 応募方法 |
申請書に必要事項を記入のうえ、サイバーメディアセンター大規模計算機システム担当(system@cmc.osaka-u.ac.jp)まで送信してください。
申請書
|
2020.11.26
サイバーメディアセンターでは、スーパーコンピュータOCTOPUS上でクラウドバースティング機能を実装いたしました。本機能を通じて、OCTOPUSでのジョブ実行と同様の方法で、マイクロソフト社のAzure上での計算が可能となっています。
クラウドバースティング機能の詳細については以下をご参照ください。
プレスリリース
本実証実験では、OCTOPUS 汎用CPUノードをご利用の皆様方を対象に、性能計測・比較、運用視点からの検証にご協力いただける方を募集いたします。検証期間は2021年3月31日(水)までを予定しています。サイバーメディアセンターでの検証が確認できた方は、サイバーメディアセンターの購入クラウド資源量がある限り、適宜ご利用いただけます。応募者多数の場合は抽選となりますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
ご興味・ご関心のあります方は募集要項、注意事項をご一読の上、是非ご応募ください。
募集要項
| 募集期間 |
12月28日(月) - 1月20日(水) |
| 検証期間 |
3月31日(水)まで |
| 応募資格 |
OCTOPUS汎用CPUノードを利用中のユーザ |
| 募集者数 |
若干数
(応募者多数の場合、お断りする可能性があります。) |
| 応募方法 |
下記のWebフォームよりお申込みください。 |
※締め切りを延長しました。
Azure上の計算ノードのハードウェア構成はOCTOPUS汎用CPUノードと一部異なります。
OCTOPUS
汎用CPUノード
|
プロセッサ:Intel Xeon Gold 6126 2基
(Skylake / 2.6 GHz 12コア × 2)
主記憶容量:192GB(ジョブで利用可能な上限は190GB)
|
Microsoft Azure
計算ノード:Standard D48ds_v4
|
プロセッサ:Intel Xeon Platinum 8272CL 1基
(Cascadelake / 2.5GHz 48コア)
主記憶容量:192GB(ジョブで利用可能な上限は190GB)
OSイメージ:CentOS 7.9 |
現在利用中のアカウントにAzure上へのジョブ投入権限を付与し、ご利用いただきます。
検証期間中も通常通りOCTOPUSへジョブ投入することが可能です。OCTOPUS上で実行したジョブはOCTOPUSポイントを消費します。
Azure上の計算ノードからOCTOPUSのストレージへアクセス可能です。OCTOPUS上にインストールされているアプリケーションも利用可能です。
今回の実証実験では、単体ノードでの実行をされている方のみを主対象とします。複数ノードでの実行をされている方も受け付けますが、ノード間通信は最大2.5Gbpsとなることにご留意ください。
詳細な利用方法は、追って担当者からご連絡いたします。
2020.09.10
概要
AVS/Expressは、流体、構造解析、医療といった様々な分野で利用される汎用可視化ソフトウェアです。本講習会では、AVS/Expressの実践的な操作方法について解説します。また15:00からは特別相談会を開催します。相談会では、AVS/Expressの利用に当たっての課題について、講師の方とご相談いただけます。講習会のみ、相談会のみの参加も可能です。
こんな方におすすめです
- AVS/Expressに興味のある方
- AVS/Expressを今後利用する予定のある方
- 「AVS可視化処理入門」受講者の方
プログラム
AVS可視化処理応用講習会
1. 「エディター」メニューの使い方
2. 色の変更(物体表面の色、カラーマップ)
3. 各種可視化手法の紹介
1) 流体解析データの可視化手法
2) 構造解析データの可視化手法
3) 離散データの可視化手法
4. 便利なモジュール
AVS可視化利用特別相談会
15:00 - 17:00
順次、専門の講師の方との相談を行っていただけます。
受講に当たってのご注意
- 新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
- 講習前にソフトウェアのインストールを⾏いますので、以下の条件を満たすPCをご⽤意ください。(インストールしたソフトウェアは、講習会後も一定期間ご利⽤頂けます。)
- CPU:1GHz以上
- メモリ:4GB以上
- グラフィック:OpenGLが動作可能
- インストールに必要なディスク容量:750MB
2020.09.10
概要
AVS/Expressは、流体、構造解析、医療といった様々な分野で利用される汎用可視化ソフトウェアです。
本講習会では、AVS/Expressの基本的な操作方法について解説します。
こんな方におすすめです
- AVS/Expressに興味のある方
- AVS/Expressを今後利用する予定のある方
プログラム
1. AVS/Express 概要
2.可視化事例紹介
3. 基本操作演習
4. 利用データに合わせた基本ネットワーク作成演習
5. データフォーマットの紹介
6. 可視化結果の保存(画像、動画、3D動画)
7. 各種可視化モジュール紹介
受講に当たってのご注意
- 新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
- 講習前にソフトウェアのインストールを⾏いますので、以下を満たすPCをご⽤意ください。(インストールしたソフトウェアは、講習会後も一定期間ご利⽤頂けます。)
- CPU:1GHz以上
- メモリ:4GB以上
- グラフィック:OpenGLが動作可能
- インストールに必要なディスク容量:750MB
2020.09.10
概要
本セミナーでは一般的なRによるプログラミングと並列化の基礎、共用計算機を用いた利用方法についてOCTOPUSを用いたハンズオン形式で行います。スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
R言語は統計解析向けのプログラミング言語環境で、Pythonと並んで機械学習のライブラリが充実していることから、様々な分野での利用が期待されています。一方で、メモリ空間を大量に利用することでも知られており、大規模なデータを解析するためには大型計算機が必要とされます。
こんな方におすすめです
- R言語を手持ちの計算機では処理しきれないデータをお持ちの方
- R言語の並列化をしたい方
受講に当たってのご注意
- 新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本セミナーはオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
- 本セミナーでは実習は行います。ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。また、こちらを参考にOCTOPUSへの接続について事前にご確認ください。
- 発行したお試しアカウントは、セミナーから1週間ご自由にお使いいただけます。
参考情報
Rの起動方法(OCTOPUS)
セミナー資料
Rハンズオンセミナー 〜OCTOPUSでRを使おう〜
2020.08.31
概要
本講習会ではOpenMPによる一般的な並列プログラミングの基礎とその利用方法を Fortran 言語及び C 言語を用いた実習により説明します。スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
OpenMPとは
OpenMPとは、プログラム中に"指示行"と呼ばれる記述を追加することでノード内並列化(共有メモリ並列処理)を行う方法です。指示行の挿入のみで並列化が可能なため、プログラミングの負担が少なく移植性が高いという利点があります。ただしノードを跨いだ並列化は行えないため、大規模な並列化を行うにはMPIと組み合わせてプログラミングを行う必要があります。なお、Fortran 言語と C 言語で記述が少し異なります。
こんな方におすすめです
- プログラムを高速化/並列化したいが、その方法がわからない方
- Unix の基礎知識(基本的なコマンドやemacs,viなどのエディタが使える)がある方
- C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
- 新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
- 本講習会では実習は行います。ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。また、こちらを参考にOCTOPUSへのログインについて事前にご確認ください。
- 発行した講習会用お試しアカウントは、講習会から1週間ご自由にお使いいただけます。
参考情報
OpenMP利用方法(SX-ACE)
OpenMP利用方法(OCTOPUS)
講習会資料
OpenMP入門
2020.08.18
本シンポジウムは終了いたしました。大変多くの方にご出席いただき、大盛況のシンポジウムとなりましたことを心よりお礼申し上げます。
(参加者数:109名)
新型コロナウイルス感染症の影響で開催を見送っておりました「Cyber HPC Symposium 2020」につきまして、プログラムの一部を変更し、Webexを⽤いたオンライン形式で「Cyber HPC Symposium 2020 Online」として開催することにいたしました。皆様のご参加をお待ちしております。
概要
開催日:2020年9月28日(月) 10:30 - 16:40 (接続受付 10:00 - )
形 式:オンライン配信
参加費:無料
主 催:大阪大学 サイバーメディアセンター
共 催:大阪大学 データビリティフロンティア機構
協 賛:学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)
ねらい
今回のシンポジウムでは、ストレージ、データ基盤の研究開発に携わる産学の専門家をお迎えし、本センターの大規模計算機システムの利活用事例、および最新の研究開発動向を踏まえつつ、高性能計算・高性能データ分析を支えるデータ基盤の今後の課題と将来を考えていきます。
プログラム
| 10:30-10:40 |
開会の挨拶 |
|
下條 真司 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
センター長・教授 |
| 10:40-11:30 |
基調講演
「SPring-8/SACLAにおけるデータ基盤の開発」 |
|
城地 保昌 |
高輝度光科学研究センター
XFEL利用研究推進室 チームリーダー |
| 11:30-12:00 |
「次期スーパーコンピュータのかたち」 |
|
伊達 進 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
応用情報システム研究部門 准教授 |
| 12:00-13:30 |
昼食休憩 |
| 13:30-14:10 |
招待講演
「DDNのHPCストレージへの貢献と新しい課題への取り組み」 |
|
井原 修一 |
株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン
Lustreエンジニアリング& I/Oベンチマーク 部長
|
| 14:10-14:50 |
「未来への挑戦:ライフデザイン・イノベーション」 |
|
八木 康史 |
大阪大学 産業科学研究所 複合知能メディア研究分野 /
データビリティフロンティア機構 ライフデザイン・イノベーション研究拠点 教授
|
| 14:50-15:00 |
休憩 |
| 15:00-16:30 |
パネルディスカッション
「HPC/HPDA融合時代のStorage/Data Management」 |
|
座長 |
渡場 康弘 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
先進高性能計算機システムアーキテクチャ共同研究部門 特任講師 |
| パネリスト |
井原 修一 |
株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン
Lustreエンジニアリング& I/Oベンチマーク 部長 |
| 大辻 弘貴 |
株式会社富士通研究所
ICTシステム研究所 エッジクラウド基盤プロジェクト |
| 片岡 洋介 |
日本電気株式会社
第一官公ソリューション事業部 主任 |
| 谷村 勇輔 |
産業技術総合研究所 人工知能研究センター
人工知能クラウド研究チーム 主任研究員 |
| 堤 誠司 |
宇宙航空研究開発機構 研究開発部門
第三研究ユニット 主任研究開発員 |
| 野崎 一徳 |
大阪大学 歯学部附属病院
医療情報室 室長・准教授 |
| 16:30-16:40 |
閉会の挨拶 |
|
下條 真司 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
センター長・教授 |
申込に当たってのご注意
本シンポジウムはオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
技術担当:Cyber HPC Symposium 2020 Online テクニカルチーム( cyberhpc-tech@cmc.osaka-u.ac.jp )
講演資料
参考資料
2020.07.10
6月に開催した講習会と同じ内容です。
概要
本講習会では一般的なMPIによる並列プログラミングの基礎と利用をFortran を用いた実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
MPIとは
MPIとは、分散メモリ並列処理におけるメッセージパッシング(複数のプロセス間でデータをやり取りするために用いるメッセージ通信操作)の標準規格のことです。
ノード間をまたがる並列化が可能となるため、その分大きなメモリ空間が利用可能になります。ただし、ユーザ自身で処理の分割やノード間の通信を指示する必要があるため、プログラミングの負担がやや大きくなります。
SX-ACEを利用する場合、MPIより簡易なノード間並列手法として「HPF」を用意しております。
こんな方におすすめです
- プログラムを高速化/並列化したいが、その方法がわからない方
- Unix の基礎知識(基本的なコマンドやemacs,viなどのエディタが使える)がある方
- C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
- 新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
- 本講習会では実習は行いませんが、ご希望の方には講習会用お試しアカウントを発行いたします。
- 発行した講習会用お試しアカウントは、講習会から1週間ご自由にお使いいただけます。
参考情報
MPI利用方法(SX-ACE)
HPF利用方法(SX-ACE)
MPI利用方法(OCTOPUS)
講習会資料
SX-ACE並列プログラミング入門(MPI)(pdf)
SX-ACE並列プログラミング入門(MPI)演習補足資料(pdf)
2020.07.10
6月に開催した講習会と同じ内容です。
概要
本講習会では、スーパーコンピュータ(OCTOPUS)で動作するプログラムの高速化を目的とした最適化及び並列化の基礎を実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
大学や高等専門学校の教員・学生であれば、誰でも受講は可能となっておりますので、お気軽にご参加いただければと思います。
こんな方におすすめです
- スーパーコンピュータ(OCTOPUS)でお手持ちのプログラムを高速化したいが、その方法がわからない方
- Unix の基礎知識(基本的なコマンドやemacs,viなどのエディタが使える)がある方
- C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
- 新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
- 本講習会では実習は行いませんが、ご希望の方には講習会用お試しアカウントを発行いたします。
- 発行した講習会用お試しアカウントは、講習会から1週間ご自由にお使いいただけます。
講習会資料
並列コンピュータ高速化技法の基礎(pdf)
2020.07.10
6月に開催した講習会と同じ内容です。
概要
本講習会では、スーパーコンピュータ(SX-ACE)で動作するプログラムの高速化を目的とし、最適化(ベクトル化)及びノード内並列化の基礎を実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
こんな方におすすめです
- SX-ACEのプログラムを高速化したいが、その方法がわからない方
- Unix の基礎的な知識(エディタが使える等)がある方
- C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
- 新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
- 本講習会では実習は行いませんが、ご希望の方には講習会用お試しアカウントを発行いたします。
- 発行した講習会用お試しアカウントは、講習会から1週間ご自由にお使いいただけます。
参考情報
ベクトル化利用方法
OpenMP/自動並列化利用方法
講習会資料
自動ベクトル化(pdf)
自動並列/OpenMP(pdf)
演習用資料(pdf)
2020.07.10
概要
本講習会ではサイバーメディアセンターのスーパーコンピュータの利用方法について学びます。大規模計算機システムを1週間自由に使用できる「無料お試しアカウント」を配布しますので、スーパーコンピュータを使った研究を検討している方に、大変おすすめできる内容となっています。
大学や高等専門学校の教員・学生であれば、誰でも受講は可能となっておりますので、お気軽にご参加いただければと思います。
こんな方におすすめです
- これからスパコンを利用する方
- Unix の基礎的な知識(エディタが使える等)がある方
- スパコンの使い方に興味がある方
受講に当たってのご注意
- 新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
- 本講習会では実習は行いませんが、ご希望の方には講習会用お試しアカウントを発行いたします。
- 発行した講習会用お試しアカウントは、講習会から1週間ご自由にお使いいただけます。
講習会資料
スパコン利用入門(pdf)
2020.07.10
概要
本説明会では、サイバーメディアセンターで運用している大規模計算機システムの概要や特徴を紹介し、その申請方法や各種利用制度について説明します。その際、次期スーパーコンピュータの調達状況について公開できる範囲で簡単に報告します。
以下のような方におすすめです
- 大規模計算機システムの利用を検討されている方
- 当センターのシステムに興味のある方
- 一般利用(有償利用)以外の利用制度を検討されている方
受講に当たってのご注意
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本説明会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
講習会資料
スパコンの概要とCMCのスパコンの紹介(pdf)
大規模計算機システムの利用(pdf)
2020.07.10
6月に開催した講習会と同じ内容です。
概要
本講習会では、並列プログラミングについて、まったくの初心者向けにその手法や考え方の基礎について紹介します。また、大規模な並列計算が可能な大型計算機やコンピュータシステムを扱うのに必要となる Unix についても、まったくの初心者でも困らないように簡単な概観を提示します。こうした並列システム、並列プログラミングについてあまり触れたことはないが興味のある方、その上で学習、研究をしようと考えている方はぜひご参加ください。
以下のような方におすすめです
- 並列計算について興味はあるが、ハードウェアやソフトウェア技術について概要がわからないので、どこから始めたら良いかわからない学生、研究者
- Unixをさわったことがあるが、様子がよくわからず勝手がつかめなかった方
- 慣れていないが、並列計算を用いて学習、研究をしようと考えている方
受講に当たってのご注意
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
講習会資料
スパコンに通じる並列プログラミングの基礎(pdf)
2020.07.01
概要
本センターのスーパーコンピュータOCTOPUSに導入されている、インテルプロセッサ上でのディープラーニング推論を高速に実行するためのソフトウェア開発環境OpenVINOツールキットの概要と利用方法について学習する。
プログラム
| 7月21日(火) |
| 13:00 - 13:05 |
開会 |
| 13:05 - 13:35 |
IntelのAI製品概要およびOpenVINO ツールキットのご紹介 |
| 13:35 - 13:50 |
ハンズオンの説明と準備 |
| 13:50 - 14:50 |
OpenVINOハンズオンPart1 事前学習済みモデルを用いた推論実行 |
| 14:50 - 15:00 |
休憩 |
| 15:00 - 16:20 |
OpenVINOハンズオンPart2 カスタムモデルを用いた推論実行およびモデルの量子化 |
| 16:20 - 16:25 |
閉会 |
※当日の進捗状況に応じて前後する可能性がございます。
受講に当たってのご注意
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本セミナーはオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。接続方法については、別途連絡いたします。
本セミナーの講師は1名のため、個人に依存したトラブルシュート等には対応しかねます。
公開資料
発表資料
2020.07.01
「学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)」は,北海道大学,東北大学,東京大学,東京工業大学,名古屋大学,京都大学,大阪大学,九州大学にそれぞれ附置するスーパーコンピュータを持つ8つの施設を構成拠点とし,東京大学情報基盤センターがその中核拠点として機能する「ネットワーク型」共同利用・共同研究拠点です。文部科学大臣の認定を受け,平成22年4月より活動を行っています。
この度、下記の通り、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)第12回シンポジウムを開催致します。今後の学際研究のさらなる発展を目指し、新たな試みとして、ポスター発表の公募と、8拠点による次年度提供資源の紹介(ポスター発表)を実施します。採択課題関係者や今後の課題応募を検討のみなさまをはじめ,情報科学および関連分野等の研究者の皆様や学生,企業・官公庁の皆様のご参加を広くお待ちしております。
第12回シンポジウム
■日 時 :2020年7月9日(木) 10:00 - 18:00
■実施形式:オンライン開催(Zoom・Slackを使用予定、情報は登録者に通知)
・オーラルセッションはウェビナー形式で実施
・ポスターセッションでは,ウェブに公開されたファイルを閲覧し,Slack上で質疑応答を実施
■参加費用:シンポジウム参加無料(事前登録をお願いします)
■申込方法:下記のページからお申込みください。
第12回シンポジウム WEBページ
■申込〆切:2020年7月6日 18:00
■主 催:学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点
- 北海道大学 情報基盤センター
- 東北大学 サイバーサイエンスセンター
- 東京大学 情報基盤センター
- 東京工業大学 学術国際情報センター
- 名古屋大学 情報基盤センター
- 京都大学 学術情報メディアセンター
- 大阪大学 サイバーメディアセンター
- 九州大学 情報基盤研究開発センター
プログラム
第12回シンポジウム WEBページをご覧ください。
問い合わせ先
JHPCN拠点事務局 jhpcn@itc.u-tokyo.ac.jp
2020.05.12
6月に開催した講習会と同じ内容です。
概要
本講習会では一般的なMPIによる並列プログラミングの基礎と利用をFortran を用いた実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
MPIとは
MPIとは、分散メモリ並列処理におけるメッセージパッシング(複数のプロセス間でデータをやり取りするために用いるメッセージ通信操作)の標準規格のことです。
ノード間をまたがる並列化が可能となるため、その分大きなメモリ空間が利用可能になります。ただし、ユーザ自身で処理の分割やノード間の通信を指示する必要があるため、プログラミングの負担がやや大きくなります。
SX-ACEを利用する場合、MPIより簡易なノード間並列手法として「HPF」を用意しております。
こんな方におすすめです
- プログラムを高速化/並列化したいが、その方法がわからない方
- Unix の基礎知識(基本的なコマンドやemacs,viなどのエディタが使える)がある方
- C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
参考情報
MPI利用方法(SX-ACE)
HPF利用方法(SX-ACE)
MPI利用方法(OCTOPUS)
講習会資料
SX-ACE並列プログラミング入門(MPI)(pdf)
SX-ACE並列プログラミング入門(MPI)演習補足資料(pdf)
2020.05.12
概要
本講習会では、スーパーコンピュータ(OCTOPUS)で動作するプログラムの高速化を目的とした最適化及び並列化の基礎を実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
大学や高等専門学校の教員・学生であれば、誰でも受講は可能となっておりますので、お気軽にご参加いただければと思います。
こんな方におすすめです
- スーパーコンピュータ(OCTOPUS)でお手持ちのプログラムを高速化したいが、その方法がわからない方
- Unix の基礎知識(基本的なコマンドやemacs,viなどのエディタが使える)がある方
- C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
講習会資料
並列コンピュータ高速化技法の基礎(pdf)
2020.05.12
概要
本講習会では、スーパーコンピュータ(SX-ACE)で動作するプログラムの高速化を目的とし、最適化(ベクトル化)及びノード内並列化の基礎を実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
こんな方におすすめです
- ・SX-ACEのプログラムを高速化したいが、その方法がわからない方
- ・Unix の基礎的な知識(エディタが使える等)がある方
- ・C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
参考情報
ベクトル化利用方法
OpenMP/自動並列化利用方法
講習会資料
自動ベクトル化(pdf)
自動並列/OpenMP(pdf)
演習用資料(pdf)
2020.05.12
概要
本講習会ではサイバーメディアセンターのスーパーコンピュータを使いながら、UNIXの基礎知識やスーパーコンピュータの利用方法について学びます。大規模計算機システムを1週間自由に使用できる「無料お試しアカウント」を配布しますので、スーパーコンピュータを使った研究を検討している方に、大変おすすめできる内容となっています。
大学や高等専門学校の教員・学生であれば、誰でも受講は可能となっておりますので、お気軽にご参加いただければと思います。
プログラム
6月26日(金)
13:30 - 14:30 スパコンの概要とCMCのスパコンの紹介
14:45 - 15:30 UNIX入門
15:45 - 17:00 スパコン利用入門
受講に当たってのご注意
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
講習会資料
スパコンの概要とCMCのスパコンの紹介(pdf)
スーパーコンピュータ利用入門(pdf)
大規模計算機システムの利用(pdf)
2020.05.07
概要
本講習会では、並列プログラミングについて、
まったくの初心者向けにその手法や考え方の基礎について紹介します。
また、大規模な並列計算が可能な大型計算機や
コンピュータシステムを扱うのに必要となる Unix についても、
まったくの初心者でも困らないように簡単な概観を提示します。
こうした並列システム、並列プログラミングについてあまり触れたことはないが興味のある方、
その上で学習、研究をしようと考えている方はぜひご参加ください。
以下のような方におすすめです
- 並列計算について興味はあるが、ハードウェアやソフトウェア技術について概要がわからないので、どこから始めたら良いかわからない学生、研究者
- Unixをさわったことがあるが、様子がよくわからず勝手がつかめなかった方
- 慣れていないが、並列計算を用いて学習、研究をしようと考えている方
受講に当たってのご注意
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本講習会はオンライン会議ツール「Webex」を用いたオンライン配信形式で行います。ネットワークに接続可能な環境をご用意ください。
講習会資料
スパコンに通じる並列プログラミングの基礎
2020.02.01
機械学習初心者の方を対象に
・ウェブアプリケーションを用いたディープラーニング
・スパコンを用いたディープラーニング
をお教えします。またプログラミング経験者の方や1日目のPBLを終えられた方には
・GPUスクラッチプログラミング
を学んでいただき,より高度な計算機利用の足掛かりにしていただければ幸いです。
注意事項:実習にはインターネットへの接続が必須です。
ネットワーク環境は各自でご用意下さい。(モバイルルーターなど)
その他事前準備(ソフトウェアのインストール等)に関して下記URLのPDFをご確認下さい。
詳細はこちらをご参照ください。
申込方法:下記メールアドレス宛にお申込ください。
hram-jim@hram.or.jp
2020.01.06
本シンポジウムにつきましては、新型コロナウイルス感染症に関する状況を鑑み、皆様方の健康・安全を配慮し、残念ながら開催を中止(延期)することといたしましたので、お知らせ申し上げます。
本シンポジウムへのご参加を予定されていた皆様、ならびにご関係の皆様には、心よりお詫び申し上げます。
概要
開催日:2020年3月19日(木) 9:30 - 17:45 (受付開始 9:00)
会 場:大阪大学サイバーメディアセンター本館(吹田キャンパス)
サイバーメディアコモンズ
参加費:無料
主 催:大阪大学 サイバーメディアセンター
共 催:大阪大学 データビリティフロンティア機構
協 賛:学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)
ねらい
本年度のシンポジウムでは、ストレージ、データ基盤の研究開発に携わる産学の専門家をお迎えし、本センターの大規模計算機システムの利活用事例、および最新の研究開発動向を踏まえつつ、高性能計算・高性能データ分析を支えるデータ基盤の今後の課題と将来を考えていきます。
プログラム
| 09:30-09:40 |
挨拶 |
|
下條 真司 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
センター長・教授 |
| 09:40-10:30 |
基調講演
「SPring-8/SACLAにおけるデータ基盤の開発」 |
|
城地 保昌 |
高輝度光科学研究センター
XFEL利用研究推進室 チームリーダー |
| 10:30-10:50 |
休憩 |
| 10:50-11:30 |
「次世代超音速エンジンに関する高性能計算機シミュレーション」 |
|
比江島 俊彦 |
大阪府立大学 大学院工学研究科
航空宇宙海洋系専攻 講師 |
| 11:30-12:00 |
「次期スーパーコンピュータのかたち」 |
|
伊達 進 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
応用情報システム研究部門 准教授 |
| 12:00-13:30 |
昼食 |
| 13:30-14:10 |
招待講演
「DDNのHPCストレージへの貢献と新しい課題への取り組み」 |
|
井原 修一 |
株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン
Lustreエンジニアリング& I/Oベンチマーク 部長
|
| 14:10-14:50 |
「未来への挑戦:ライフデザイン・イノベーション」 |
|
八木 康史 |
大阪大学 産業科学研究所 複合知能メディア研究分野 /
データビリティフロンティア機構 ライフデザイン・イノベーション研究拠点 教授
|
| 14:50-15:30 |
「実験とシミュレーションの連携による液体の物理学の発展に向けて」 |
|
岩下 拓哉 |
大分大学 理工学部
共創理工学科 准教授 |
| 15:30-16:15 |
休憩 |
| 16:15-17:45 |
パネルディスカッション
「HPC/HPDA融合時代のStorage/Data Management」 |
|
座長 |
渡場 康弘 |
大阪大学 サイバーメディアセンター
先進高性能計算機システムアーキテクチャ共同研究部門 特任講師 |
| パネリスト |
井原 修一 |
株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン
Lustreエンジニアリング& I/Oベンチマーク 部長 |
| 大辻 弘貴 |
株式会社富士通研究所
ICTシステム研究所 データシステムプロジェクト |
| 片岡 洋介 |
日本電気株式会社
第一官公ソリューション事業部 主任 |
| 谷村 勇輔 |
産業技術総合研究所 人工知能研究センター
人工知能クラウド研究チーム 主任研究員 |
| 堤 誠司 |
宇宙航空研究開発機構 研究開発部門
第三研究ユニット 主任研究開発員 |
| 野崎 一徳 |
大阪大学 歯学部附属病院
医療情報室 室長・准教授 |
| 18:00- |
レセプション |
|
場所:銀杏クラブ(銀杏会館内) 会費:2500円
▼銀杏会館の場所 吹田キャンパスマップ 11番
吹田キャンパスマップ[pdf] |
参考資料
2019.11.27
サイバーメディアセンターでは、スーパーコンピュータOCTOPUS上でクラウドバースティング機能を実装いたしました。本機能を通じて、OCTOPUSでのジョブ実行と同様の方法で、マイクロソフト社のAzure上での計算が可能となっています。
クラウドバースティング機能の詳細については以下をご参照ください。
プレスリリース
本実証実験では、OCTOPUS 汎用CPUノードをご利用の皆様方を対象に、性能計測・比較、運用視点からの検証にご協力いただける方を募集いたします。検証期間は2019年12月27日(金)までを予定しています。応募者多数の場合は抽選となりますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
ご興味・ご関心のあります方は募集要項、注意事項をご一読の上、是非ご応募ください。
募集要項
| 募集期間 |
12月4日(水) - 12月11日(水) |
| 応募資格 |
OCTOPUS汎用CPUノードを利用中のユーザ |
| 募集者数 |
若干数
(応募者多数の場合、お断りする可能性があります。) |
| 応募方法 |
下記のWebフォームよりお申込みください。 |
注意事項
Azure上の計算ノードのハードウェア構成はOCTOPUS汎用CPUノードと一部異なります。
OCTOPUS
汎用CPUノード
|
プロセッサ:Intel Xeon Gold 6126 2基
(Skylake / 2.6 GHz 12コア × 2)
主記憶容量:192GB(ジョブで利用可能な上限は190GB)
|
Microsoft Azure
計算ノード
|
プロセッサ:Intel Xeon Platinum 8168 1基
(Skylake / 2.7GHz 24コア)
主記憶容量:96GB(ジョブで利用可能な上限は95GB) |