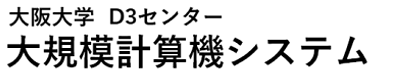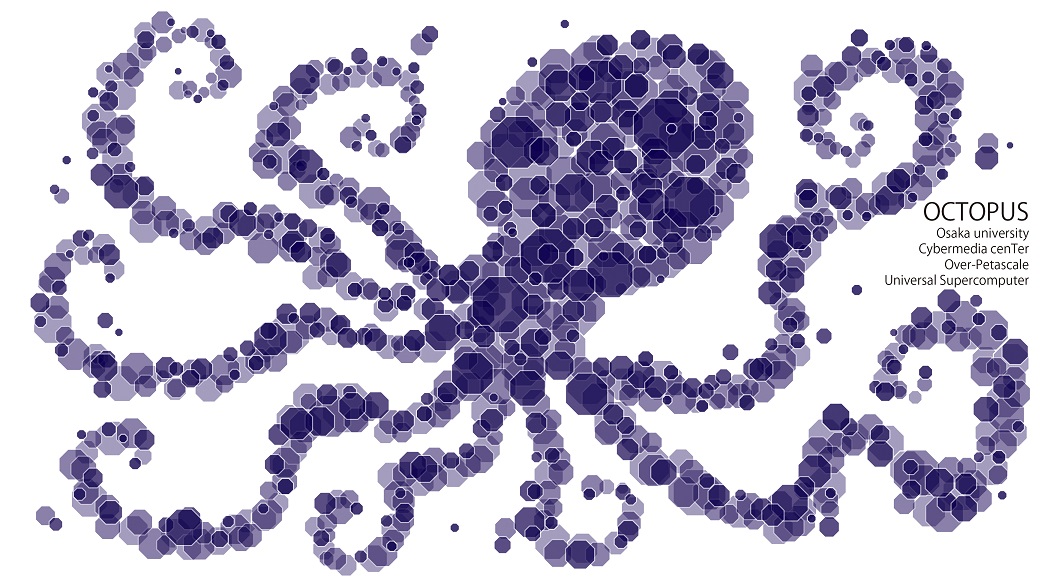2017.08.18
概要
AVS/Expressは、流体、構造解析、医療といった様々な分野で利用される汎用可視化ソフトウェアです。
本講習会では、AVS/Expressの基本的な操作方法について解説します。
また15:00からは特別相談会を開催します。
相談会では、AVS/Expressの利用に当たっての課題や、
本センターの24面大型立体表示システムを使った大規模可視化手法などについて、
専門の講師の方との対面相談を行っていただけます。
講習会のみ、相談会のみの参加も可能です。
対象者
AVS/Expressに興味のある方
「AVS可視化処理入門」受講者の方
AVS/Expressを今後利用する予定のある方 / 利用を迷っている方
AVS/Expressを利用している方/これから利用される方
プログラム
AVS可視化処理応用講習会
10:00 - 15:00(適宜休憩を挟みます)
1. 各種可視化手法の紹介
1)流体解析データを利用した可視化手法
等値面、断面、ベクトル、流線、パーティクルトレースなど
2)構造解析データを利用した可視化手法変形など
2. その他、テクニックの紹介
3. 可視化結果の保存方法の紹介
画像、動画、形状
4. 無償ビューアーの紹介
AVS可視化利用特別相談会
15:00 - 17:00
順次、専門の講師の方との対面相談を行います。
受講に当たってのご注意
講習前に、ソフトウェアのインストールを行いますので、以下の条件を満たすノートPCをお持ちください。
推奨動作環境: CPU:1GHz以上 メモリ:256MB以上、グラフィック:OpenGLが動作可能、
インストールに必要なディスク容量:600MB
インストールしたソフトウェアは、受講後もご利用頂けます。
2017.08.18
概要
AVS/Expressは、流体、構造解析、医療といった様々な分野で利用される汎用可視化ソフトウェアです。
本講習会では、AVS/Expressの基本的な操作方法について解説します。
対象者
AVS/Expressに興味のある方
AVS/Expressを今後利用する予定のある方
プログラム
1. AVS/Express 概要
2. 可視化事例紹介
3. モジュールの基本操作
4. 表示物の基本操作
5. 利用データに合わせた表示方法の紹介(ネットワーク)
6. データフォーマットの紹介
受講に当たってのご注意
講習前に、ソフトウェアのインストールを行いますので、以下の条件を満たすノートPCをお持ちください。
推奨動作環境: CPU:1GHz以上 メモリ:256MB以上、グラフィック:OpenGLが動作可能、
インストールに必要なディスク容量:600MB
インストールしたソフトウェアは、受講後もご利用頂けます。
2017.07.20
概要
本セミナーでは、大規模連立一次方程式を求解する直接法ソフトウェアパッケージについて解説し、スーパースカラー型並列計算機 VCC、ベクトル型並列計算機 SX-ACE での利用法を紹介します。
目次
・直接法概観
・疎行列データ格納形式、CSR
・直接法ソフトウェアパッケージの利用
初期化、シンボリック分解、数値分解、前進後退代入、終了処理の手続について
・VCC/SX-ACE でのライブラリーのリンク方法
こんな方におすすめです
・流体、構造、電磁場解析などの数値シミュレーションで連立一次方程式を解きたい方
・マルチコアCPUと共有メモリー構成での並列計算に興味のある方
・C、Fortran によるプログラム経験がある方
備考
・座学および実習からなるセミナーです。
・ネットワークに接続可能で、ターミナルソフトのインストールされたノートPCをお持ちください
・スーパーコンピュータSX-ACE、VCCを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
直接法について
工学や物理学での流体、構造、電磁場解析など数値シミュレーションでは偏微分方程式を離散化して生じる大規模な連立の線形あるいは非線形の方程式を解く必要があります。非線形問題は Newton 法などによって線形化することで、最終的に大規模な疎行列からなる連立一次方程式を解くことになります。
疎行列解法には LU 分解により構成される直接法と共役勾配法などに代表される反復法があります。直接法は非線形性が強い問題から得られた行列、あるいは異なる物理係数により条件数が大きい行列などの反復法が苦手とする行列に対しても安定して求解できますが、計算量が多い問題点があります。一方、反復法は計算量は少ないが、反復計算の収束は問題に強く依存し現実的な時間内に収束しない場合もあります。
本セミナーでは近年のソフトウェア技術の進歩と数学理論の発展により並列化が可能になり、計算効率が向上している直接法を取り上げます。サイバーメディアセンターの VCC では Intel MKL に付属する Pardisoソフトウェアおよび、オープンソースソフトウェアの MUMPS と Dissection が利用できます。また、SX-ACE では後者の2つのソフトウェアが利用できます。セミナー後半ではこれらのソフトウェアの利用法を解説し実習を行ないます。これらの直接法ソフトウェアは共有メモリーのマルチコア CPU 構成で稼動するため、既存のコードの計算時間を短縮することが容易にできます。また Dissection は4倍精度演算も可能なため、倍精度演算による求解では精度が不足する問題もターゲットとすることができます。
公開資料
講演資料(pdf)
実習用ソースコード(.tar.gz)
2017.07.20
内容は6月に開催した講習会と同様のものになります。
概要
本講習会ではHPFを用いて指示行の追加のみでスーパーコンピュータ(SX)で動作する分散並列プログラムを作成する方法の基礎を説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
HPFとは
HPF(High Performance Fortran)は、Fortranの分散メモリ型並列計算機向け拡張仕様です。
Fortranプログラムに対してコメント形式の指示行を挿入することで、分散並列化が行えるため、
MPIに比べ習得が容易です。
サイバーメディアセンターで運用しているSX-ACEで、HPFを利用することが可能です。
※SX以外の計算機では利用環境がありませんのでご注意ください。
こんな方におすすめです
・大規模並列化について興味があるが、簡易に大規模並列化を行いたい方
・Unix の基礎的な知識(エディタが使える等)がある方
・C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
講習会では実習を行いますので、ネットワークに接続可能なノートPCを必ずお持ちください。
また、ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。
参考情報
MPI利用方法(SX-ACE)
HPF利用方法(SX-ACE)
配布資料
SX-ACE並列プログラミング入門(HPF)(pdf)
2017.07.20
内容は6月に開催した講習会と同様のものになります。
概要
本講習会では一般的なMPIによる並列プログラミングの基礎と利用をFortran を用いて実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
MPIとは
MPIとは、分散メモリ並列処理におけるメッセージパッシング(複数のプロセス間でデータをやり取りするために用いるメッセージ通信操作)の標準規格のことです。
ノード間をまたがる並列化が可能となるため、その分大きなメモリ空間が利用可能になります。ただし、ユーザ自身で処理の分割やノード間の通信を指示する必要があるため、プログラミングの負担がやや大きくなります。
SX-ACEを利用する場合、MPIより簡易なノード間並列手法として「HPF」を用意しております。講習会はこちらからお申込みください。
こんな方におすすめです
・大規模並列化について興味がある方
・Unix の基礎的な知識(エディタが使える等)がある方
・C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
講習会では実習を行いますので、ネットワークに接続可能なノートPCを必ずお持ちください。
また、ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。
参考情報
MPI利用方法(SX-ACE)
HPF利用方法(SX-ACE)
配布資料
SX-ACE並列プログラミング入門(MPI)(pdf)
SX-ACE並列プログラミング入門(MPI)演習補足資料(pdf)
2017.07.19
概要
大阪大学サイバーメディアセンターでは、汎用CPUノード群、メニーコア型ノード群、GPU計算ノード群、大容量主記憶計算ノード群、大容量ストレージから構成される、総理論演算性能1.46PFlopsを有するハイブリッド型スーパーコンピュータ OCTOPUSの運用を開始いたします。
本チャレンジ企画では、OCTOPUS導入を記念し、来たるべきGPU計算ノード群の最大限の利活用を目的として、利用者の皆様方より当該ノード群で性能向上が見込まれるプログラムを募集し、お手持ちのプログラム(非商用)を本センターで預かり、NVIDIAの専門家のご支援のもと、OCTOPUSで導入予定のGPUノード群に最適化を行います。
OCTOPUSシステムのGPUノードは、高速インターコネクトNVLinkによって接続されるNVIDIA製GPU Tesla P100を4基搭載し、64GB(16GB x 4)のGPUメモリ空間とメモリ空間(192GB)が統一されたユニファイドメモリ(Unified Memory)を提供し、高並列処理を実現可能です。
本チャレンジ企画では、SX-ACEによるベクトル処理とTesla P100の比較という側面から、本センターのベクトル型スーパーコンピュータSX-ACEを1ノードで利用されている利用者のプログラムを対象とします。
SX-ACEノードとOCTOPUSのGPUノードの性能比較をしてみたい方、なんとなく興味がある方、等々、ご興味・ご関心のあります方は是非ご応募ください。
募集要項
| 募集期間 |
平成29年10月3日-15日 |
| 応募資格 |
本センター大規模計算機システムのユーザ |
| 対象プログラム |
本センターのSX-ACE 1ノードで実行しているプログラム |
| 対象プログラム数 |
若干数 |
| 応募方法 |
下記のWebフォームよりお申込みください。追って担当者よりご連絡いたします。
|
2017.07.13
大阪大学サイバーメディアセンターでは、9月12日(火)の13:30より、本センターが利用負担金を全額支援する公募型利用制度の説明会を開催いたします。
概要
本センターでは、大規模計算機システムを活用する研究開発の育成・高度化支援の観点から、今後の発展が見込まれる萌芽的な研究課題や、本センターの大規模計算機システムを最大限活用することで成果が見込まれる研究課題を公募しております。
「公募型利用制度」は、今後の発展が見込まれる萌芽的な研究課題を募集する「若手・女性研究者支援萌芽枠」と、大規模計算機システムを最大限活用することで成果が見込まれる研究課題を募集する「大規模HPC支援枠」から構成され、採択された場合は利用負担金が全額免除されます。
本説明会では、「公募型利用制度」の詳細をご説明するほか、具体的に申し込みを検討されている方向けの相談会も実施いたします。
多数の皆様方のご参加をお待ちしております。
スケジュール
開催日時 :平成29年9月12日(火)13:30 - 15:00
プログラム:13:30 - 14:00 説明会
14:00 - 15:00 相談会
参考情報
公募型利用制度とは 平成29年度公募型利用制度 採択実績
2017.07.08
内容は6月に開催した講習会と同様のものになります。
概要
本講習会では、並列コンピュータ(VCC,OCTOPUS)で動作するプログラムの高速化を目的とした最適化及び並列化の基礎を実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
大学や高等専門学校の教員・学生であれば、誰でも受講は可能となっておりますので、お気軽にご参加いただければと思います。
こんな方におすすめです
- ・並列コンピュータ(VCC,OCTOPUS)でお手持ちのプログラムを高速化したいが、その方法がわからない方
- ・Unix の基礎的な知識(エディタが使える等)がある方
- ・C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
講習会では実習を行いますので、ネットワークに接続可能なノートPCを必ずお持ちください。
また、ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。
配布資料
並列コンピュータ高速化技法の基礎(pdf)
2017.07.08
内容は6月に開催した講習会と同様のものになります。
概要
本講習会では、スーパーコンピュータ(SX)で動作するプログラムの高速化を目的とし、最適化(ベクトル化)及びノード内並列化の基礎を実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
こんな方におすすめです
- ・SX-ACEのプログラムを高速化したいが、その方法がわからない方
- ・Unix の基礎的な知識(エディタが使える等)がある方
- ・C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
講習会では実習を行いますので、ネットワークに接続可能なノートPCを必ずお持ちください。
また、ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。
参考情報
ベクトル化利用方法
OpenMP/自動並列化利用方法
講習会資料
自動ベクトル化(pdf)
自動並列/OpenMP(pdf)
演習用資料(pdf)
2017.07.08
内容は6月に開催した講習会と同様のものになります。
概要
サイバーメディアセンターのスパコンを使いながら、UNIXとスパコンの基礎知識や利用方法について学びます。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きですので、スパコンをこれから使ってみようと考えている方に、大変おすすめできる内容となっています。
大学や高等専門学校の教員・学生であれば、誰でも受講は可能となっておりますので、お気軽にご参加いただければと思います。
プログラム
9月4日(月)
13:30 - 14:30 スパコンの概要とCMCのスパコンの紹介
14:45 - 16:00 UNIX入門
16:15 - 17:30 スパコンを使った演習
受講に当たってのご注意
講習会では実習を行いますので、ネットワークに接続可能なノートPCを必ずお持ちください。
また、ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。
講習会資料
スパコンの概要とCMCのスパコンの紹介(pdf)
スーパーコンピュータ利用入門(pdf)
大規模計算機システムの利用(pdf)
2017.07.08
本講習会のみ豊中キャンパスでの開催となります。ご注意ください。
内容は6月に開催した講習会と同様のものになります。
概要
本講習会では、並列プログラミングについて、まったくの初心者向けにその手法や考え方の基礎について紹介します。
また、大規模な並列計算が可能な大型計算機やコンピュータシステムを扱うのに必要となる Unix についても、まったくの初心者でも困らないように簡単な概観を提示します。こうした並列システム、並列プログラミングについてあまり触れたことはないが興味のある方、その上で学習、研究をしようと考えている方はぜひご参加ください。
以下のような方におすすめです
- ・ 並列計算について興味はあるが、ハードウェアやソフトウェア技術について概要がわからないので、どこから始めたら良いかわからない学生、研究者
- ・ Unixをさわったことがあるが、様子がよくわからず勝手がつかめなかった方
- ・ 慣れていないが、並列計算を用いて学習、研究をしようと考えている方
講習会資料
スパコンに通じる並列プログラミングの基礎(pdf)
2017.07.05
本コンテストの募集は終了しました。たくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。
結果
最優秀賞:宮本 要子 様
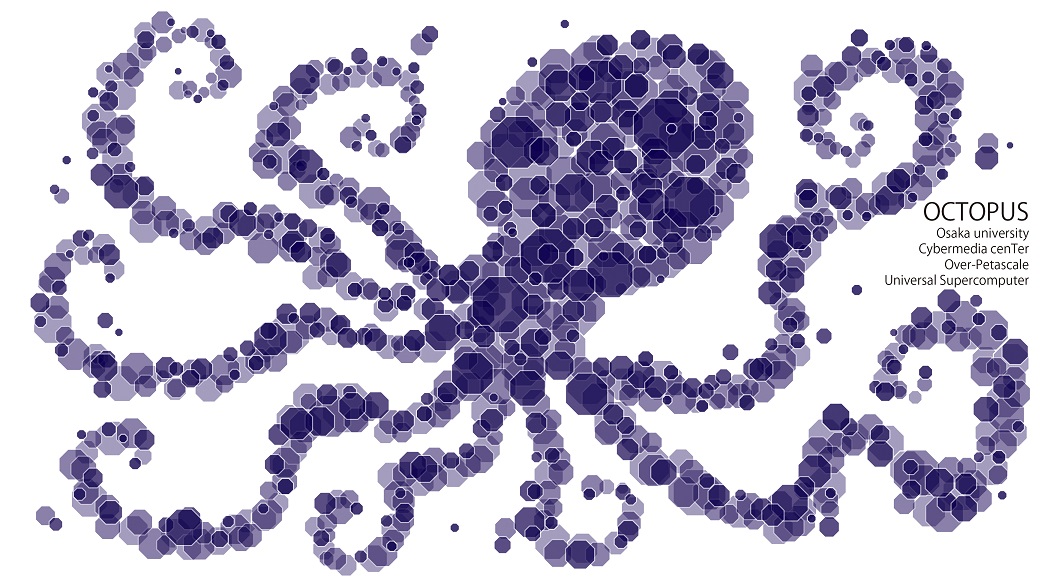
----
スーパーコンピュータをキャンバスに絵を描いてみませんか?
大阪大学サイバーメディアセンターでは、2017年12月に日本全国の大学、研究所、企業の研究者が利用可能なスーパーコンピュータシステム「OCTOPUS (Osaka university Cybermedia cenTer Over-Petascale Universal Supercomputer)」 の運用を開始いたします。
スーパーコンピュータOCTOPUSの導入・運用開始を記念して、今後のOCTOPUSの”顔”となるデザインを募集いたします。
採用されたデザインは、本センターのデータセンタであるITコア棟内の設置エリアに配置される計算ラック群(1940mm x 3500mm)に描画されます。また、本センターのウェブページ、広報資料等、幅広く利用されます。
締切
2017年9月20日 作品提出・応募締め切り、必着
賞
最優秀賞(1点) ノートパソコン、表彰状
募集内容
「OCTOPUS」のデザイン
下記のキーワードから想像されるデザイン
「大阪」
「皆に愛される」
「最先端の科学研究」
「スーパーコンピュータ」

「OCTOPUS」計算ラック群
白抜きの箇所にデザインを描画いたします

「OCTOPUS」計算ラック群
平面図

「OCTOPUS」計算ラック群
デザイン掲載イメージ
提出物
作品
200dpi以上の解像度
1940 x 3500の比率
カラー
作品データはJPEGで提出すること
コンセプト説明
参加方法
提出物を下記提出先までメールにて送付
参加資格
不問
参加費
無し
審査員
大阪大学サイバーメディアセンター、日本電気株式会社で構成する審査委員会
結果発表
2017年9月下旬、入賞者に通知
本センターキャンペーンサイトにて発表予定
著作権の扱い
応募作品の所有権並びに入賞作品の著作権(著作権法第27条、第28条の権利を含む)は大阪大学サイバーメディアセンターに帰属
主催
大阪大学 サイバーメディアセンター
協賛
特定非営利活動法人 バイオグリッドセンター関西、日本電気株式会社


提出先・問い合わせ先
| 提出先・問い合わせ先 |
E-mail:system@cmc.osaka-u.ac.jp
〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘5-1
大阪大学サイバーメディアセンター本館 1階事務室
情報推進部情報基盤課研究系システム班
大規模計算機システム担当宛
|
2017.06.07
SupercomputingContest2017を2017年8月21日-26日に開催します。
開催スケジュール
予選課題発表 :2016年5月31日(水) 正午 発表予定
参加申し込み締切:2016年6月16日(金) 正午必着
本戦 :2016年8月22日(月) - 8月26日(金)
概要
SupercomputingContestは、スーパーコンピュータを駆使した高校生のプログラミング大会です。
予選を通過した10組のチーム(1チーム2~3名)が大阪大学、東京工業大学の会場に分かれ、スーパーコンピュータを使ったプログラミングを行います。数日間かけて本選課題の問題を解くプログラムを作成し、作成最終日に提出されたプログラムの正確さ・速度を審査委員会が評価し、コンテスト最終日の成果報告会で発表します。本選課題には、科学技術の様々な分野から最先端の話題が選ばれ、それを高校生にもわかりやすい問題にして、皆さんに挑戦してもらいます。
詳細
参加方法やコンテストの詳細については公式WEBサイトをご覧ください。
公開資料
ポスター
2017.06.07
本講習会は東北大学サイバーサイエンスセンターからの映像配信による講習会となります
概要
非経験的分子軌道計算プログラムとして広く使用されている
ソフトウェア「Gaussian」の入門講座として、基本的な使い方から紹介します。
「Gaussian」は大阪大学サイバーメディアセンターでもサービス提供しており、
これから利用してみたい、という方にお勧めの内容となっております。
受講に当たっては、以下の点にご注意ください。
1.講習内容は、東北大学の講習会をTV会議システムを
使用して受信するという形になりますので、
システムの違いや制約が あることを予めご了承願います。
2.大阪大学では実習は行いません。
東北大学では15:00~17:00で実習を行いますが、
大阪大学では15:00で講習会配信を終了します。
3.ネットワークや機材等の不調により、当日においても中止する場合がありますので、
予めご了承願います。
関連情報
東北大学 サイバーサイエンスセンター 大規模科学計算システム
東北大学 サイバーサイエンスセンター 講習会ページ
2017.06.02
本プログラムでは、皆様方が研究室で開発・利用されている、お手持ちのプログラムを本センターで預かり、本センターの大規模計算機での利用ができるよう支援します(*)。これにより、本センター大規模計算機システムを今後利用していただけることが見込まれるプログラムを募集いたします。
ご興味・ご関心のあります方は是非ご応募ください。
(*)プログラムの大幅な変更が必要になる場合においては、一部のサポートとなります。
対象者
| 氏名 |
所属 |
| 荻野 陽輔 様 |
大阪大学 工学研究科 |
| 松尾 一輝 様 |
大阪大学 レーザー科学研究所 |
募集要項
| 募集期間 |
平成29年8月10日-30日 |
| 応募資格 |
本センター 大規模計算機システムの利用を検討している方 |
| 対象プログラム数 |
若干数 |
| 応募方法 |
下記のWebフォームよりお申込みください。追って担当者よりご連絡いたします。
|
※受付は終了しました。本プログラムは試行サービスでありますため、次回の開催は未定です。
2017.06.02
本プログラムでは、お手持ちのプログラム(非商用)を本センターで預かり、大規模計算機に対する最適化および並列化を行います。最適化、並列化することにより、本センター大規模計算機システムを最大限利活用することが見込まれるプログラムを募集いたします。
ご興味・ご関心のあります方は是非ご応募ください。
対象者
| 氏名 |
所属 |
| 鈴木 恒雄 様 |
金沢大学 自然科学研究科 |
| 塚原 隆裕 様 |
東京理科大学 理工学部 機械工学科 |
| 若山 将征 様 |
理化学研究所 |
本プログラムへのご感想
この度、大阪大学サイバーメディアセンター(CMC)および日本電気株式会社(NEC)のご厚意・ご尽力により、流体力学研究で用いる直接数値計算(DNS)コードの高効率なMPI化を実現することができた。当該DNSは、固体壁に挟まれた流れが起こす乱流遷移のプロセス・メカニズムを解明することを目的としており、遷移中に観察される局在乱流の大規模パターン形成を十分に捉えるために非常に大規模な計算となる。乱流遷移は一世紀以上続く古典的な問題であるが、発達の目覚ましい大型計算機の恩恵により実験困難な流路サイズで流れのシミュレーションが可能となってきており、乱流解明の更なるブレイクスルーが期待されている。この度の高効率なMPI-DNS計算により、乱流遷移に潜む臨界現象の普遍性を遂に見出せるものと考えている。当該チューニングに際して、プログラム上の誤り修正、効率的なFFT処理法の提案、より大規模な計算を見据えたMPI化、細やかなコメント追加まで施して頂いた。これらは今後のコード最適化を行う上での重要であり、並列計算機の活用が一層進むであろう。重ねて、CMCとNECにお礼を申し上げたい。
(東京理科大 塚原様)
全体の実行時間に対して、Bank Conflict の時間が大きな割合を占めていることが気になっていました。今回のチューニングプログラムでBank Conflict の時間に対する改善点をご指摘いただき、全体で約1.2倍の高速化が実現できたことを嬉しく思います。
(理化学研究所 若山様)
募集要項
| 募集期間 |
平成29年8月10日-30日 |
| 応募資格 |
本センター 大規模計算機システムのユーザ |
| 対象プログラム数 |
若干数 |
| 応募方法 |
下記のWebフォームよりお申込みください。追って担当者よりご連絡いたします。
|
※本プログラムは試行サービスでありますため、次回の開催は未定です。
過去の実績
平成28年度
2017.05.12
「学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)」は,北海道大学,東北大学,東京大学,東京工業大学,名古屋大学,京都大学,大阪大学,九州大学にそれぞれ附置するスーパーコンピュータを持つ8つの施設を構成拠点とし,東京大学情報基盤センターがその中核拠点として機能する「ネットワーク型」共同利用・共同研究拠点です。文部科学大臣の認定を受け,平成22年4月より活動を行っています。
この度,下記の通り,学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)第9回シンポジウムを開催致します。
当シンポジウムでは,平成28年度に実施された共同研究課題39件の研究成果を口頭発表で報告し,平成29年度に採択された共同研究課題46件の研究内容をポスターセッションで紹介いたします。あわせて、平成28年度および平成29年度に採択された萌芽型共同研究課題から27件のポスター発表があります。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
第9回シンポジウム
■日 時 :2016年7月13日(木) 10:00 - 18:30 (懇親会:18:30 - 20:00), 14日(金) 10:00 - 17:30
■場 所 :THE GRAND HALL(品川)
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー 3F
■定 員 :250名
■参加費用:シンポジウム参加無料(事前登録をお願いします)
懇親会4,000円(当日、受付で現金にて申し受けます)
■申込方法:下記のページからお申込みください。
第9回シンポジウム WEBページ
■申込〆切:2017年7月4日(火) 17:00
■主 催:学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点
- 北海道大学 情報基盤センター
- 東北大学 サイバーサイエンスセンター
- 東京大学 情報基盤センター
- 東京工業大学 学術国際情報センター
- 名古屋大学 情報基盤センター
- 京都大学 学術情報メディアセンター
- 大阪大学 サイバーメディアセンター
- 九州大学 情報基盤研究開発センター
プログラム
第9回シンポジウム WEBページをご覧ください。
問い合わせ先
JHPCN拠点事務局 jhpcn@itc.u-tokyo.ac.jp
2017.05.08
概要
本講習会ではHPFを用いて指示行の追加のみでスーパーコンピュータ(SX)で動作する分散並列プログラムを作成する方法の基礎を説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
HPFとは
HPF(High Performance Fortran)は、Fortranの分散メモリ型並列計算機向け拡張仕様です。
Fortranプログラムに対してコメント形式の指示行を挿入することで、分散並列化が行えるため、
MPIに比べ習得が容易です。
サイバーメディアセンターで運用しているSX-ACEで、HPFを利用することが可能です。
※SX以外の計算機では利用環境がありませんのでご注意ください。
こんな方におすすめです
・大規模並列化について興味があるが、簡易に大規模並列化を行いたい方
・Unix の基礎的な知識(エディタが使える等)がある方
・C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
講習会では実習を行いますので、ネットワークに接続可能なノートPCを必ずお持ちください。
また、ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。
参考情報
MPI利用方法(SX-ACE)
HPF利用方法(SX-ACE)
配布資料
SX-ACE並列プログラミング入門(HPF)(pdf)
2017.05.08
概要
本講習会では一般的なMPIによる並列プログラミングの基礎と利用をFortran を用いて実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
MPIとは
MPIとは、分散メモリ並列処理におけるメッセージパッシング(複数のプロセス間でデータをやり取りするために用いるメッセージ通信操作)の標準規格のことです。
ノード間をまたがる並列化が可能となるため、その分大きなメモリ空間が利用可能になります。ただし、ユーザ自身で処理の分割やノード間の通信を指示する必要があるため、プログラミングの負担がやや大きくなります。
SX-ACEを利用する場合、MPIより簡易なノード間並列手法として「HPF」を用意しております。講習会はこちらからお申込みください。
こんな方におすすめです
・大規模並列化について興味がある方
・Unix の基礎的な知識(エディタが使える等)がある方
・C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
講習会では実習を行いますので、ネットワークに接続可能なノートPCを必ずお持ちください。
また、ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。
参考情報
MPI利用方法(SX-ACE)
HPF利用方法(SX-ACE)
配布資料
SX-ACE並列プログラミング入門(MPI)(pdf)
SX-ACE並列プログラミング入門(MPI)演習補足資料(pdf)
2017.05.08
概要
本講習会では、並列コンピュータ(VCC,HCC)で動作するプログラムの高速化を目的とした最適化及び並列化の基礎を実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
大学や高等専門学校の教員・学生であれば、誰でも受講は可能となっておりますので、お気軽にご参加いただければと思います。
こんな方におすすめです
- ・並列コンピュータ(VCC,HCC)でお手持ちのプログラムを高速化したいが、その方法がわからない方
- ・Unix の基礎的な知識(エディタが使える等)がある方
- ・C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
講習会では実習を行いますので、ネットワークに接続可能なノートPCを必ずお持ちください。
また、ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。
配布資料
並列コンピュータ高速化技法の基礎(pdf)
2017.04.27
概要
本講習会では、スーパーコンピュータ(SX)で動作するプログラムの高速化を目的とし、最適化(ベクトル化)及びノード内並列化の基礎を実習により説明します。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きです。
こんな方におすすめです
- ・SX-ACEのプログラムを高速化したいが、その方法がわからない方
- ・Unix の基礎的な知識(エディタが使える等)がある方
- ・C, Fortran によるプログラム経験がある方
受講に当たってのご注意
講習会では実習を行いますので、ネットワークに接続可能なノートPCを必ずお持ちください。
また、ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。
参考情報
ベクトル化利用方法
OpenMP/自動並列化利用方法
講習会資料
自動ベクトル化(pdf)
自動並列/OpenMP(pdf)
演習用資料(pdf)
2017.04.27
概要
サイバーメディアセンターのスパコンを使いながら、UNIXとスパコンの基礎知識や利用方法について学びます。
スーパーコンピュータを1週間自由に使える「無料お試しアカウント」付きですので、スパコンをこれから使ってみようと考えている方に、大変おすすめできる内容となっています。
大学や高等専門学校の教員・学生であれば、誰でも受講は可能となっておりますので、お気軽にご参加いただければと思います。
プログラム
6月13日(火)
13:30 - 14:30 スパコンの概要とCMCのスパコンの紹介
14:45 - 16:00 UNIX入門
16:15 - 17:30 スパコンを使った演習
受講に当たってのご注意
講習会では実習を行いますので、ネットワークに接続可能なノートPCを必ずお持ちください。
また、ターミナルソフト(TeraTermなど)を使用しますので、あらかじめインストールをお願いいたします。
講習会資料
スパコンの概要とCMCのスパコンの紹介(pdf)
スーパーコンピュータ利用入門(pdf)
大規模計算機システムの利用(pdf)
2017.04.26
概要
本講習会では、並列プログラミングについて、
まったくの初心者向けにその手法や考え方の基礎について紹介します。
また、大規模な並列計算が可能な大型計算機や
コンピュータシステムを扱うのに必要となる Unix についても、
まったくの初心者でも困らないように簡単な概観を提示します。
こうした並列システム、並列プログラミングについてあまり触れたことはないが興味のある方、
その上で学習、研究をしようと考えている方はぜひご参加ください。
以下のような方におすすめです
・並列計算について興味はあるが、ハードウェアやソフトウェア技術について概要が
わからないので、どこから始めたら良いかわからない学生、研究者
・Unixをさわったことがあるが、様子がよくわからず勝手がつかめなかった方
・慣れていないが、並列計算を用いて学習、研究をしようと考えている方
講習会資料
スパコンに通じる並列プログラミングの基礎(pdf)
2017.02.21
本プログラムでは、お手持ちのプログラム(非商用)を本センターで預かり、大規模計算機に対する最適化および並列化を行います。最適化、並列化することにより、本センター大規模計算機システムを最大限利活用することが見込まれるプログラムを募集いたします。
ご興味・ご関心のあります方は是非ご応募ください。
※受付は終了しました。多数のご応募ありがとうございました。
対象者
| 氏名 |
所属 |
| 石橋 春佳 様 |
大阪大学 大学院工学研究科 |
| 佐久間 悠人 様 |
東京工業大学 大学院総合理工学研究科 |
| 千徳 靖彦 様 |
大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター |
| 坪井 伸幸 様 |
九州工業大学 大学院工学研究院 |
| 比江島 俊彦 様 |
大阪府立大学 学術情報センター |
| 吉田 尚史 様 |
信州大学 工学部 |
募集要項
| 募集期間 |
平成29年1月19日-27日 |
| 応募資格本センター |
大規模計算機システムのユーザ |
| 対象プログラム数 |
若干数 |
| 応募方法 |
下記のWebフォームよりお申込みください。追って担当者よりご連絡いたします。
※受付は終了しました。多数のご応募ありがとうございました。 |
2017.01.06
本シンポジウムは開催終了いたしました。大変多くの方にご出席いただき、大盛況のシンポジウムとなりましたことを心よりお礼申し上げます。
(参加者数:98名)
概要
開催日:2017年3月16日 9:30 - 17:45 (受付開始 9:00)
会 場:大阪大学サイバーメディアセンター本館(吹田キャンパス)
サイバーメディアコモンズ
参加費:無料
主 催:大阪大学 サイバーメディアセンター
共 催:大阪大学 データビリティフロンティア機構
協 賛:学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)
ねらい
本年度のシンポジウムでは、高性能計算・高性能データ分析に携わる産学の専門家をお迎えし、本センターの大規模計算機システム・可視化システムの利活用事例、および最新の研究開発動向を踏まえつつ、高性能計算および高性能データ分析を支える計算基盤をテーマに考えます。
参加を希望される方は、ページ下部のウェブ申し込みフォームから直接お申込みくださいませ。
※事前申込受付は終了しました。事前申し込みに間に合わなかった方も、現地にて当日受付が可能ですので、ぜひご参加くださいませ。
プログラム
| 09:30-09:40 |
挨拶 |
|
下條 真司 |
大阪大学
サイバーメディアセンター センター長・教授 |
| 09:40-10:30 |
基調講演
「第4次産業革命を牽引するHPCとAIの融合基盤」 |
|
関口 智嗣 |
産業技術総合研究所
情報・人間工学領域 領域長 |
| 10:30-10:50 |
休憩 |
| 10:50-11:30 |
「人工知能と高性能コンピューティング」 |
|
松下 康之 |
大阪大学
大学院情報科学研究科 マルチメディア工学専攻
データビリティフロンティア機構 知能情報基盤部門 教授 |
| 11:30-12:00 |
「全国共同利用大規模並列計算システムの概要」 |
|
伊達 進 |
大阪大学
サイバーメディアセンター 応用情報システム研究部門 准教授 |
| 12:00-13:30 |
昼食 |
| 13:30-14:10 |
招待講演
「AIテクノロジーと将来への展望」 |
|
根岸 史季 |
インテル株式会社
データセンター・グループ・セールス
アジアパシフィック・ジャパン HPC担当ディレクター |
| 14:10-14:50 |
「塩分成層流体における乱流の大規模直接数値シミュレーション」 |
|
沖野 真也 |
京都大学
大学院工学研究科 機械理工学専攻 助教 |
| 14:50-15:30 |
「Big Healthcare Data Analytics: Challenges and Applications」 |
|
Chonho Lee |
大阪大学
サイバーメディアセンター 先進高性能計算機システムアーキテクチャ共同研究部門 特任准教授 |
| 15:30-16:15 |
休憩(24面大型立体表示システムのデモあり) |
| 16:15-17:45 |
パネルディスカッション
「HPC(High Performance Computing)とHPDA(High Performance Data Analysis)を支える計算基盤」 |
|
座長 |
木戸 善之 |
大阪大学
サイバーメディアセンター 応用情報システム研究部門 講師 |
| パネリスト |
杉浦 敦 |
日本SGI株式会社
営業統括本部 ビジネスデベロップメント部 ジャパン・セールス・マネージャー |
| 中島 耕太 |
株式会社富士通研究所
コンピュータシステム研究所 データシステムプロジェクト 主管研究員 |
| 長友 英夫 |
大阪大学
レーザーエネルギー学研究センター レーザー核融合学研究部門 准教授 |
| 中村 良介 |
産業技術総合研究所
人工知能研究センター 地理情報科学研究チーム 研究チーム長 |
| 細見 岳生 |
日本電気株式会社
システムプラットフォーム研究所 研究部長 |
| 18:00- |
レセプション |
|
場所:銀杏クラブ(銀杏会館内) 会費:2500円
▼銀杏会館の場所 吹田キャンパスマップ 11番
吹田キャンパスマップ[pdf] |
ご講演資料
・第4次産業革命を牽引するHPCとAIの融合基盤(産業技術総合研究所 関口 智嗣 様)
・塩分成層流体における乱流の大規模直接数値シミュレーション(京都大学 沖野 真也 様)
・Big Healthcare Data Analytics: Challenges and Applications(大阪大学 Chonho Lee)
参考資料
・ポスター
・パンフレット
2017.01.06
概要
開催日:2017年3月15日(水)14:00-17:00
会 場:大阪大学サイバーメディアセンター本館(吹田キャンパス)
サイバーメディアコモンズ
参加費:無料
プログラム
|
14:00-14:05 |
挨拶 |
|
|
菊池 誠 |
大阪大学
サイバーメディアセンター 教授 |
| [若手・女性研究者支援萌芽枠 セッション I] |
| |
14:05-14:35 |
「鼻咽腔閉鎖時における流路トポロジー変化が呼気に及ぼす影響」 |
|
|
野崎 一徳 |
大阪大学
歯学部附属病院 助教 |
| |
14:35-15:05 |
「キロテスラ級磁場下における超高強度レーザープラズマ相互作用の物理」 |
|
|
畑 昌育 |
大阪大学
レーザーエネルギー学研究センター 特任研究員 |
|
15:05-15:15 |
休憩 |
| [大規模HPC支援枠] |
| |
15:15-15:45 |
「格子量子色力学を使った高密度物質の研究」 |
|
|
河野 宏明 |
佐賀大学
大学院工学系研究科 教授 |
| |
15:45-16:15 |
「初期宇宙における銀河形成と巨大ブラックホール形成」 |
|
|
長峯 健太郎 |
大阪大学
大学院理学研究科 教授 |
|
16:15-16:30 |
休憩 |
| [若手・女性研究者支援萌芽枠 セッション II] |
| |
16:30-17:00 |
「固液界面における和周波発生分光スペクトルの第一原理シミュレーション」 |
|
|
大戸 達彦 |
大阪大学
大学院基礎工学研究科 助教 |
※発表は25分、質疑は5分の予定です。
2016.12.02
概要
大阪大学サイバーメディアセンターでは、国内の学術機関との連携により、情報通信(ICT)技術を応用した高等教育に向けた取り組み・研究、ならびに、高等教育のグローバル化に対応した取り組み・研究の成果報告・情報共有することを目的とし、大学ICT推進協議会(AXIES)が毎年主催する年次大会において研究発表、研究展示を行っています。
発表内容
2016年度の年次大会では、企画セッション「HPCテクノロジー」において、下記2件の本センター所属の教職員が関係した研究発表を行います。
(1) 多様化する計算要求に柔軟に対応できる計算基盤の実現に向けて
(2) タイルドディスプレイのためのタブレット端末を用いたシームレスな操作手法の開発
セッション: [FA1] HPCテクノロジーⅠ
日時:12月16日(金) 9:00-10:30
発表:多様化する計算要求に柔軟に対応できる計算基盤の実現に向けて
著者:伊達進(大阪大学)、吉川隆士(大阪大学)、高橋雅彦(NEC システムプラットフォーム研究所)、菅真樹(NEC システムプラットフォーム研究所)、渡場 康弘(奈良先端科学技術大学院大学)、Chonho Lee(大阪大学)、木戸善之(大阪大学)、下條真司(大阪大学)
セッション: [FA3] HPCテクノロジーⅢ
日時:12月16日(金) 13:30-15:00
発表:タイルドディスプレイのためのタブレット端末を用いたシームレスな操作手法の開発
著者:鈴木拓馬(大阪大学)、清川清(大阪大学)、竹村治雄(大阪大学)
掲載:大学ICT推進協議会 2015年度年次大会 論文集,TBA
関連情報
大阪大学 AXIESのWEBサイト
AXIES WEBサイト
2016.11.08
九州大学 情報基盤研究開発センターにて、代表的なフリーソフトウェアである Julia とFreeFem++ の実習付きチュートリアルを開催します.(共催:大阪大学 サイバーメディアセンター)
参加をご希望の方は下記のページを御覧ください。
九州大学 情報基盤研究開発センターHP 案内ページ
※申込期限は,11月18日(金)となります。
科学技術計算専用言語 Julia
日時
講師
降籏 大介 氏(大阪大学 サイバーメディアセンター)
概要
Julia はマサチューセッツ工科大学 (MIT) で開発された科学技術計算専用言語でMatlab や Python によく似た使いやすさと C 言語や Fortran と同等の高速さを兼ね備えた最先端軽量プログラミング言語として注目されています.Julia の文法は科学技術計算に適しており,BLAS, LAPACK, GMP などの定番ライブラリが最初から組み込まれています.整数・実数の任意精度計算,並列計算,オブジェクト指向のさらに先の多重ディスパッチをサポートしています.1,000 以上のユーザ作ライブラリ (Package) が公式に登録されています.C, Python,Fortran などの他の言語との相互呼び出しが可能であり,外部プログラムの呼び出しなどのシェル的な利用もできます.ドキュメントも完備されており,ユーザコミュニティも活発です.MIT ライセンスとしてフリーかつオープンソースであることも大きな特長です.
本チュートリアルでは, Julia 言語そのものについての入門的解説から始め,非線形偏微分方程式の求解を例にした Julia による数値解析手法の紹介,および並列計算について解説します.
プログラム
| 13:00 - 14:10 |
Julia 言語そのものについて入門的解説 |
| 14:25 - 15:35 |
Julia 言語による数値解析
- 非線形偏微分方程式を例にして |
| 15:50 - 17:00 |
Julia 言語による並列計算 |
FreeFem++ による有限要素プログラミング
日時
講師
鈴木 厚 氏(大阪大学 サイバーメディアセンター)
概要
FreeFem++ はパリ第六(ピエールマリーキュリー)大学の J.-L. Lions 研究所のF. Hecht 教授らによる有限要素法ソフトウェアパッケージです.有限要素メッシュの生成,離散化行列の線形ソルバーおよび可視化の一式を網羅しているため,ユーザーは数理モデルの構築,時間発展の離散化,非線形問題の解法に専念にできます.弱形式の離散化プロセスを専用のスクリプト言語とデータ構造で非常に簡単に記述できるところが,通常の専用あるいは汎用有限要素解析ソフトウェアとの大きな違いです.
もともとは数値計算の教育を目的として作られましたが,並列計算や 3次元要素を扱う機能を拡張し,有限要素法によるシミュレーションのプロトタイプ実行を実現する優れたソフトウェアになっています.
FreeFem++ は非常に強力なツールですが,その反面,ソフトウェアを使いこなすためには有限要素法の数学的記述法とスクリプト言語記述の知識が必要になります.本チュートリアルでは,代表的な偏微分方程式の弱形式による記述法から始め,剛性行列の記述方法と連立一次方程式ソルバーの利用法,非線形反復の実現方法を概観します.3次元計算では,連立一次方程式を GMRES 法などの反復法で解くことになりますが,適切な前処理を選択することが高速計算のためには重要になります.直接法を部分的に取り込んだ Additive Schwarz 法による前処理を紹介します.
プログラム
| 10:00 - 11:00 |
偏微分方程式と弱形式
- Poisson 方程式,Navier-Stokes 方程式,静磁場方程式 |
| 11:15 - 12:15 |
弱形式から有限要素剛性行列へ
- 疎行列と連立方程式,非線形反復のための Newton 法 |
| 13:45 - 14:45 |
FreeFem++ 言語
- matrix, array, for loop, function |
| 15:00 - 17:00 |
3次元問題と実習
- Additive Schwarz 前処理による GMRES 法を用いた反復解法 |
参考リンク
2016.09.27
2016年11月13日-18日の会期で米国ユタ州ソルトレイクシティで開催される国際会議・国際展示会SC16において、サイバーメディアセンターの研究ブース出展を行います。
サイバーメディアセンター出展の詳細はこちらからご覧頂けます。
概要
大阪大学サイバーメディアセンターでは、わが国および欧米諸国の研究機関、大学、企業に対して、本センターでの研究成果の報告、利用促進を主目的とし、毎年11月に米国で開催される高性能計算、ネットワーク、ストレージ、解析技術に関する国際会議・展示会 SC(Super Computing) に2000年より研究展示ブースを出展しています。
※SC: The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis の通称。IEEE Computer SocietyおよびACMSIGARCHが主催する、高性能計算、ネットワーク、ストレージ、解析技術をテーマとした最高峰の国際会議および最大級の展示会。
関連情報
SC16の公式WEBサイト
サイバーメディアセンター SCでの活動
2016.09.27
概要
本センターでは、昨年度成果報告を提出頂きました利用者様から、マルチノード化により、さらなる研究成果が見込まれると思われる利用者様を中心に、特別相談会の案内を送付しております。
本相談会では、SX-ACE導入業者である日本電気株式会社よりチューニングのエキスパートを招き、利用者様方へのプログラムへの分析や最適化のアドバイスを実施いたします。SX-ACEでより高精度かつ高速な計算を実現するための有意義なご提案ができればと考えております。
内容
・SX-ACEの利用方法、チューニング方法の解説
・利用者様のプログラム最適化、アドバイス
・HPCIやJHPCNへの申請アドバイス
※プログラムは事前にお預かりすることにより、より有益なアドバイスを提供可能です。